はじめに|その「大丈夫かな?」が、大切なきっかけになります
久しぶりに祖父母に会う予定はありますか?
もし「なんとなく、前と違うかも」と感じたら、それはあなたにしか気づけない、大切なサインかもしれません。
同じ話を繰り返す、以前は出来ていたスマホの操作がうまくいかない――
そんな“変化”を、どうか見逃さないでください。
そして、もし帰省してきた家族からそんな声を受け取ったら、「歳をとるってそういうことよ」となんて流さず、検査を受けてもらうことを考えてほしいのです。
認知症は、早く気づけた方が選べる道が広がります。
帰省してきた家族の「大丈夫かな?」が、家族の未来と尊厳を守る一歩になります。
若いあなたへ|祖父母と会ったとき、こんな変化を見逃さないで
同じ話を繰り返す、言葉が出にくいみたい…それ、もしかして?
たとえば、こんなことに気づいたことはありませんか?
- 同じ話を何度もするようになった
- 話のテンポが変わった、噛み合いにくくなった
- 言おうとしている言葉が、すぐに出てこない
- 財布やスマホ、薬の置き場所を忘れていた
- いつものスマホ操作ができなくなっていた
こうした変化は、加齢とともに自然なこともあります。
でも、もしかしたらそれは、認知機能の変化のはじまりかもしれません。
久しぶりに会ったからこそ気づける違和感は、実はとても貴重です。
毎日一緒にいる人ほど見逃してしまう、小さな変化。
それに気づけるのは、あなたのような“離れて暮らす家族”なのです。
伝える相手は“親”でいい。あなたの言葉が家族を助けます
「でも、誰に言えばいいの?」
そんなときは、まずは親に伝えてみてください。
「ちょっとだけ気になったんだけど…」
そのひと言が、あとで「あのとき言ってくれてよかった」と言われる日につながるかもしれません。
親世代のあなたへ|「歳をとるってそういうことよ」と流さずに、耳を傾けてほしい
久しぶりに会った家族だからこそ気づける“違和感”
お子さんが「おじいちゃん(おばあちゃん)、なんか前と違うかも。大丈夫かな。」と話してきたとき、どうかその声を流さずに受け止めてみてください。
ふだん一緒に暮らしていると気づきにくい変化でも、離れて暮らす家族には”違和感”として気づくことがあります。
その”離れて暮らす家族の違和感”は、家族にとってとても貴重です。
次に「必要だ」と感じた時のために。今は「試しに」くらいで十分
「何か困っているわけじゃないし…」と思うかもしれませんが、一度だけでも検査や相談をしておくと、次に「必要だ」と感じた時に動きやすくなります。
その時に「またたぶん大丈夫だと思うけど、検査に行ってみようか」と言えること。
ご本人にとっても「行ったことがある場所」そして「たぶんまた大丈夫」と思えることで、検査へのハードルが低くなるかと思います。
早期発見ができると、選べる未来が増える
認知症は、早く気づくことでサポートの選択肢が広がります。
症状の進行をゆるやかにすることができるかもしれませんし、本人の意思を反映した生活設計を立てたりすることもできます。
👇こちらのサイトに早期発見について詳しく書かれています
東京都福祉局-とうきょう認知症ナビ-認知症の基礎知識-認知症に早く気づくことが大事!
おわりに|そのひと言が、家族を守る“最初のサイン”になるかもしれません
帰省や再会は、離れて暮らす家族がつながる貴重な機会です。
そのタイミングで生まれた“ちょっとした違和感”こそが、家族にとっての大切な最初のサインになることがあります。
ご本人にとっても、ご家族にとっても、“早めに気づける”ことは、生活と尊厳を守る、とても大切で幸運なことだと思います。
その機会を、どうか大切にしてください。
👇もう少し詳しく知りたいと感じたら、介護の入り口に読んで良かった本を紹介していますので、よければご覧ください
最後まで読んでくれたあなたに|ChatGPTおみやげプロンプト🎁
ChatGPTにコピペして使ってみてね!
認知症の検査を祖父母に受けさせたい時、孫のどんな一言があると効果的ですか?
【📋コピーする】「おみやげプロンプトってなに?」「ChatGPTをダウンロードしたい」と思った方へ
👉 おみやげプロンプトの楽しみ方・使い方をまとめた記事はこちら
※この記事は、筆者個人の体験と気づきを記録したものです。
判断に迷う場合は、ご自身で抱え込まず、地域の包括支援センターやかかりつけ医など、公的な窓口・医療機関にご相談ください。
下記は、認知症や高齢者支援についての基本的な情報がまとまった信頼できるサイトです。
「もしかして…?」と思ったときは、まずはここから確認してみるのもおすすめです。
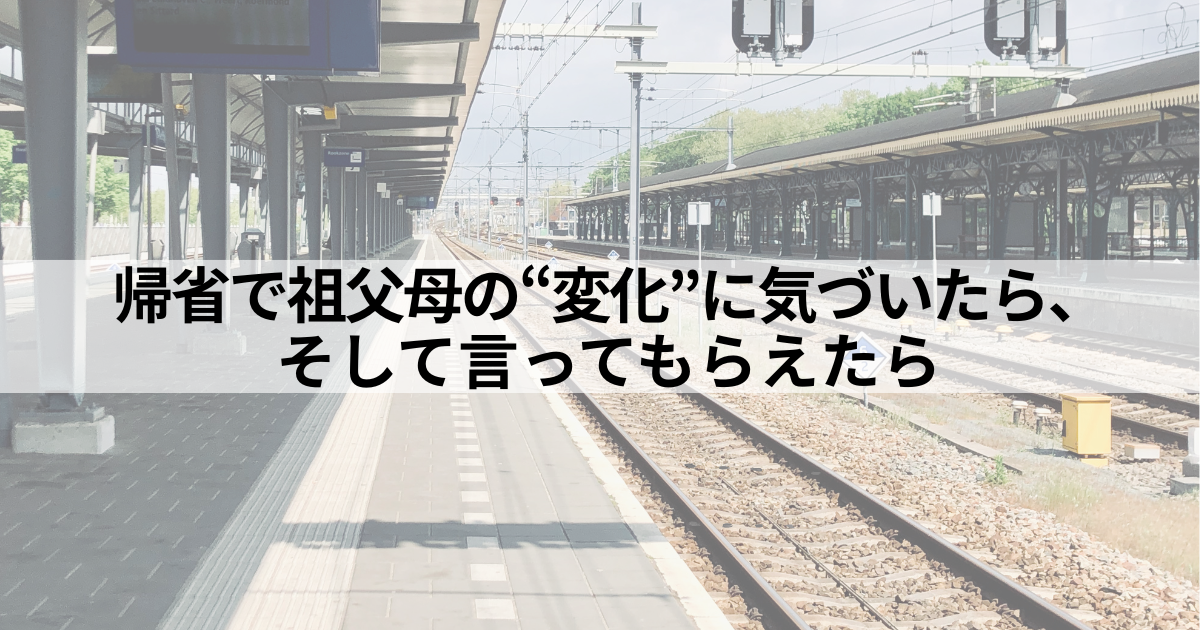
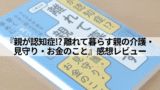

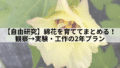
コメント